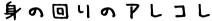


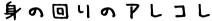


折角の休日もやる事が無いともったいない!という事で前回の更新から全然間が無いですが作ってみました。今回の品はスターリングエンジンです。

Stirlingengine AL2
「スターリングエンジン」と言われても馴染みの無い言葉である人が多いかと思われるので、簡単な説明をしてみます。
スターリングエンジンは1816年にRobert Stirling牧師によって発明された外燃機関(外燃機関とは燃やすものと仕事をする作動流体が別の機関で、蒸気機関もこれに当たります。対する内燃機関は現在のガソリンエンジンなど)。危険な事故の多発する蒸気機関に代わるものとして考え出されました。
仕組みとしては、気体が熱せられた際には膨張、冷却された際には収縮する性質を応用しています。この模型では、加熱にはアルコールランプの炎、冷却にはフィンによる外気との熱交換を用いています。ガソリンエンジンのように爆発しないため騒音は摩擦の音くらいですし、熱源は何でも良いので場合によっては排ガスも出さず非常にクリーンなのが利点なわけです。重要な要素の一つとして「ディスプレーサ」という部分があるのですが、私が説明するよりもネット上での解説を読まれた方が分かりやすいでしょうから省かせて頂きます。興味のある方はGoogle等で「スターリングエンジン」の検索をしてみて下さい。
右下にある黒い容器がアルコールランプ。燃料用アルコールを注ぎ、火をつけ、しばらくあったまるのを待ちます。あったまったかな?と思ったらはずみ車を軽く回してやると…。

勢い良く回りはじめます。加熱部と冷却部の温度差が大きいほどよく回る事になるので、例えば冷却部をファンヒーターの風に当てると回転数がガクンと落ちたりします。最高回転数は聞いた所によると2500[rpm]。rpm=revolution per minuteで1分間に回転する回数。つまり1秒間に41.7回転近くしているわけです。速い!

右から見たところ。だいたい対称の構造をしています。

左から見たところ。2つのはずみ車の間にベルトを通して動力を他の機関に伝達する事ができるようになっています。とは言っても、非常に小さな力なので指で簡単に止まっていまうくらいです。可能なら発電機でもつけてみようかなと思っていましたがトルクが足りず難しそう。
しかしこれを蒸気機関車に取り付けた方もいらっしゃるそうで…加工・応用技術とも凄いなぁ。

買った時、一緒に燃料用アルコールがついてきました。メタノールとエタノールの混合物だと思われます。薬局等で入手できるらしい。

精密機器のため、稼動部にホコリがたまると悪影響を与えます。とうわけで装飾の意味も含めて普段はこのようなアクリルケースに入れてます。寸法を指定してアクリルを扱う専門店に作ってもらいました。品物の料金は割安だったけど送料が高かった。
写真だけじゃ分からない所もあると思うので動画も撮ってみました。WebCamだとフレームレートが低すぎてさっぱり映らないのでデジカメの動画撮影機能を使っています。そのためファイル形式はmovとなっていて、QuickTime等で再生できます。
mov形式動画その1(4.1MB)
mov形式動画その2(1.4MB)
その2では結局フレームレートが足らなくなってマトリックスの特殊効果みたいになってる様子が見られます(笑)
スターリングエンジンは実用へはまだまだ問題も多く、現在研究が進められているエンジンです。太陽熱や地熱といった、無駄になってしまっているものからエネルギーを吸収できるようになれば素晴らしいでしょうね。
少しタイプは違いますが、「大人の科学」からもスターリングエンジンのキットが出ています。興味を持たれた方はぜひどうぞ。